
社会人で勉強時間が確保できないけど、それでも資格って取れるの?

資格の勉強時間が取れない場合の対処法は?

時間がない中でも取れそうな資格ってあるの?
と疑問を抱えていませんか?
この記事では、以下の内容をお届けします。
- 社会人でも少ない勉強時間で取れる資格の選び方
- 働きながらでも取れる社会人におすすめの資格9選!
- 社会人が資格の勉強時間を捻出できない5つの理由
- 社会人が資格の勉強時間を生み出す4つの方法
この記事を最後まで読むことで、忙しい社会人でも資格のための勉強ができるようになります。 「勉強したいのに、時間がなくてどうしよう…」という不安が解消されるはずです。
ぜひ参考にしてみてください。
この記事を書いた人

たけみやたいが
資格のミカタを運営している、ライター歴4年のたけみやと申します。「スキルを身に着けたい」「資格を取りたい」という相談がめちゃめちゃ集まってくる人。実際に相談者さんの夢をかなえた経験が、指折で数えられないほどはあります。どうやって学習を進めて行けばよいか相談に乗ることには自信がありますし、一緒に新しい景色をみるのが好きです。一緒に資格取得を目指しましょう!
社会人でも少ない勉強時間で取れる資格の選び方
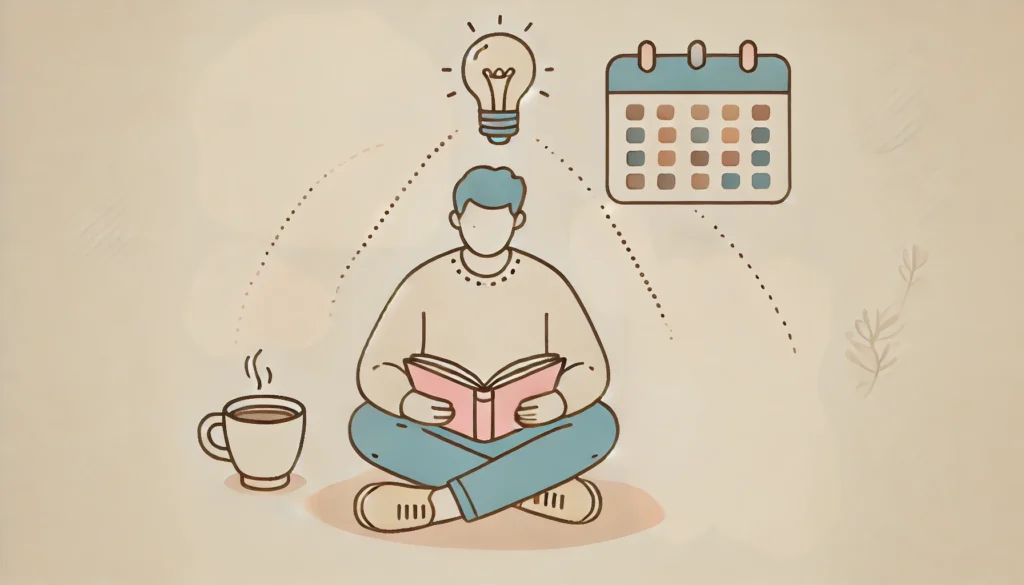

社会人だから勉強時間があまりとれない…
と不安を抱えている方もいるでしょう。
せっかく、キャリアアップのために資格を取ろうとしているのに、時間が割けず取得に踏み切れないのはもったいないですよね。
そんな方は、まず選び方を知り、自分が少ない勉強時間で取れそうかを確認してみましょう。
社会人でも少ない勉強時間で取れる資格の選び方は、4つあります。
- 合格にかかる時間が短い資格を選ぶ
- 自分が持っている知識が活かせる資格を選ぶ
- 受験資格がない
- 楽しみながら取れる資格を選ぶ
それぞれ詳しく解説します。
合格にかかる時間が短い資格を選ぶ
まずは、合格にかかる時間が短い資格を選ぶことが大切です。少ない時間で確実に取得するために、タイパの良い資格を選定することをおすすめします。
たとえば、以下のような資格は合格にかかる時間が比較的短いです。
- ファイナンシャル・プランニング技能士(FP技能士)
- ウェブデザイン技能士
- ITパスポート
- MOS
- 色彩検定3級
- 医療事務(医療事務認定実務者(R)試験)
これらの資格は1か月程度で取得できるため、スピード感を持って取り組めますよ。
ちなみに、以下の記事では1か月で取れる資格を18選紹介しているので、興味があれば、ぜひ参考にしてみてください。
自分が持っている知識が活かせる資格を選ぶ
自分が持っている知識が活かせそうな資格を選択することも大切です。知識0の状態から勉強するのと、ある程度基礎知識を持っていて、そこに専門知識を追加するのとでは、かかる時間が全く異なるからです。
たとえば、MOS資格を取得する際にExcelを使用したことがない人であれば、基礎的な操作方法から学ぶ必要があります。しかし、基礎知識がある方なら追加でマクロの知識などを習得するだけでいいので、スムーズに進みます。
また、今後のキャリアパスにも大きく影響するので、自分が持っている知識を活かせる資格を選択しましょう。
受験資格がない
受験資格が設定されていないものを選ぶことで、どなたでも取得が可能です。たとえば、司法試験を受けるためには、以下の受験資格を満たす必要があります。
- 法科大学院過程の修了
- 司法試験予備試験の合格
- 法科大学院課程の在学及び法第4条第2項第1号に規定する学長の認定
つまり、資格を取るための要件が厳しいほど、スタートラインに立つための手間・努力が必要なので、社会人が簡単に取得するのは困難です。
楽しみながら取れる資格を選ぶ
楽しみながら取れる資格を選ぶことで「勉強時間=趣味」と考えられるので、辛いと感じることなく、学習が可能です。
たとえば、私はデザインの学校に通っていた経験があり、普段からポスターを見たりするのが好きなので、色彩検定を取得することはほかの資格と比較して苦しくありません。
このように、自分が好きな分野の資格を取得すると、楽しみながらスキルを身に着けられますよ。
働きながらでも取れる社会人におすすめの資格9選!

それでは、働きながらでも取れる社会人におすすめの資格を9つ紹介します。
- 不動産取引の専門資格:宅地建物取引士(宅建士)
- 企業の財務を支える会計の専門資格:日商簿記検定2級
- 人生設計について学べる資格:ファイナンシャルプランナー(FP技能検定2級)
- ビジネスに役立つITの基礎知識が学べる資格:ITパスポート
- 労務管理と社会保険が学べる資格:社会保険労務士(社労士)
- 法務手続きのエキスパート資格:行政書士
- 電気設備の技術者になれる資格:第二種電気工事士
- 危険物管理の専門資格:危険物取扱者(乙種)
- 快適な住環境を支えるマンション管理の資格:マンション管理士・管理業務主任者
それぞれ詳しく解説します。
不動産取引の専門資格:宅地建物取引士(宅建士)
宅地建物取引士(宅建士)は、不動産取引における重要事項の説明や契約書への記名・押印など、専門的な業務を行うための国家資格です。不動産業界での信頼性向上やキャリアアップに役立ちます。
以下に、宅建士資格に関する主要な項目をまとめた表を作成しました。
| 項目 | 内容 |
| 費用 | – 受験手数料:8,200円 – 登録実務講習費用:約20,000円前後(実務経験が2年未満の場合) |
| 学習時間 | – 初学者の場合:200~300時間が目安 |
| 試験の内容 | – 試験形式:四肢択一のマークシート方式 – 問題数:全50問 – 主な出題範囲: – 権利関係(民法、不動産登記法など) – 宅建業法 – 法令上の制限(都市計画法、建築基準法など) – 税その他(不動産取得税、固定資産税など) |
| 資格の要件 | – 受験資格:年齢・学歴・国籍に関係なく誰でも受験可能 – 資格登録要件: – 宅建士試験合格 – 宅地建物取引業の実務経験2年以上、または登録実務講習の修了 – 登録の欠格要件に該当しないこと |
| 得られる知識 | – 不動産取引に関する法律知識 – 不動産に関する税法の知識 – 不動産の需給や価格評価に関する知識 |
| 合格率 | – 平均合格率:約15~17% |
宅建士資格の取得は、不動産業界での活躍を目指す方にとって大きなメリットがあります。計画的な学習と試験対策を行い、合格を目指しましょう。
企業の財務を支える会計の専門資格:日商簿記検定2級
日商簿記検定2級は、企業の財務を支えるための重要な会計専門資格です。この資格を取得することで、商業簿記と工業簿記の知識を深め、中規模の株式会社の財務諸表を理解し、製造業における原価計算のスキルを身につけることができます。
これらの知識は、経理や財務部門でのキャリアアップや、経営状況の的確な把握に役立ちます。
以下に、日商簿記検定2級に関する情報をまとめた表を作成しました。
| 項目 | 内容 |
| 費用 | – 統一試験受験料:4,720円 – ネット試験受験料:4,720円 – 教材費用:数千円程度 – 講座受講料(任意):数万円程度 |
| 学習時間 | – 簿記3級合格者:100~200時間 – 初学者:150~250時間 – 1日2時間の学習で、約2~4ヶ月が目安 |
| 試験内容 | – 商業簿記:仕訳、財務諸表の作成、連結会計など – 工業簿記:原価計算、標準原価計算、直接原価計算など – 試験時間:90分 – 合格基準:100点満点中70点以上 |
| 資格要件 | – 受験資格:特になし – 年齢や学歴に関係なく受験可能 |
| 得られる知識 | – 商業簿記:中小企業の財務諸表の読み方、リース取引や外貨建取引の処理 – 工業簿記:製造業における原価計算、差異分析、利益計画の立案 |
| 合格率 | – 統一試験:平均20%前後(回によって変動あり) – ネット試験:平均30%前後 |
日商簿記検定2級の取得は、企業の財務管理や経営分析において大いに役立ちます。特に、経理や財務部門でのキャリアを目指す方や、経営者として財務状況を正確に把握したい方にとって、非常に有益な資格といえるでしょう。
人生設計について学べる資格:ファイナンシャルプランナー(FP技能検定2級)
ファイナンシャルプランナー(FP)技能検定2級は、人生設計に必要な知識を学べる資格です。この資格を取得することで、ライフプランニングや資産運用、税金、不動産、相続など、個人の生活設計に欠かせない幅広い知識を身につけることができます。
これらの知識は、個人の資産管理や将来設計に役立つだけでなく、金融業界や保険業界などでのキャリアアップにも有益です。
以下に、FP技能検定2級に関する情報をまとめた表を作成しました。
| 項目 | 内容 |
| 費用 | – 学科試験:5,700円 – 実技試験:6,000円 – 学科・実技両方受験:11,700円 – 教材費用:数千円程度 – 講座受講料(任意):数万円程度 |
| 学習時間 | – 必要学習時間:150~300時間 – 1日2時間の学習で、約2.5~5ヶ月が目安 |
| 試験内容 | – 学科試験:ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、タックスプランニング、不動産、相続・事業承継の6分野から出題 – 実技試験:選択した試験機関と科目により異なる(例:資産設計提案業務、個人資産相談業務など) |
| 資格要件 | – 3級FP技能検定合格者 – 2年以上の実務経験者 – AFP認定研修の修了者 |
| 得られる知識 | – ライフプランニング:教育資金や老後資金の計画 – リスク管理:保険商品の知識と選び方 – 金融資産運用:投資商品の分析と選択 – タックスプランニング:所得税や相続税の知識 – 不動産:不動産の評価と取引 – 相続・事業承継:相続法や事業継承の基本 |
| 合格率 | – 学科試験:40~50%前後 – 実技試験:50~60%前後 |
FP技能検定2級の取得は、個人の資産管理や将来設計に大いに役立ちます。特に、金融や保険業界でのキャリアを目指す方や、自身の人生設計をより充実させたい方にとって、非常に有益な資格といえるでしょう。
ビジネスに役立つITの基礎知識が学べる資格:ITパスポート
ITパスポートは、ビジネスに役立つITの基礎知識を学べる国家資格です。この資格を取得することで、情報技術だけでなく、経営戦略やマネジメントなど、現代のビジネスに必要な幅広い知識を身につけることができます。これらの知識は、業種や職種を問わず、ビジネスパーソンとしての基礎力向上に役立ちます。
以下に、ITパスポート試験に関する情報をまとめた表を作成しました。
| 項目 | 内容 |
| 費用 | – 受験料:7,500円(税込) – 教材費用:数千円程度 – 講座受講料(任意):数万円程度 |
| 学習時間 | – IT知識がある方:100~150時間 – 初学者:150~200時間 – 1日2時間の学習で、約1.5~3ヶ月が目安 |
| 試験内容 | – ストラテジ系(経営全般):35問程度 – マネジメント系(IT管理):20問程度 – テクノロジ系(IT技術):45問程度 – 試験時間:120分 – 合格基準:総合評価点600点以上(1000点満点)、かつ各分野で300点以上 |
| 資格要件 | – 受験資格:特になし – 年齢や学歴に関係なく受験可能 |
| 得られる知識 | – 経営戦略やマーケティングの基本 – ITサービスマネジメントやプロジェクトマネジメントの基礎 – セキュリティやネットワークなどのIT基礎知識 |
| 合格率 | – 平均50%前後 |
ITパスポートの取得は、ビジネスにおけるIT活用能力の証明となり、就職・転職活動やキャリアアップにおいて有利に働きます。特に、ITの基礎知識を身につけたいと考えている方や、ビジネス全般の知識を強化したい方にとって、有益な資格といえるでしょう。
労務管理と社会保険が学べる資格:社会保険労務士(社労士)
社会保険労務士(社労士)は、労務管理や社会保険に関する専門知識を有し、企業の人事・労務部門で重要な役割を担う国家資格です。
この資格を取得することで、労働基準法や社会保険制度など、労働者の権利や福利厚生に関する幅広い知識を身につけることができます。これらの知識は、企業の労務管理の適正化や従業員の働きやすい環境づくりに貢献します。
以下に、社会保険労務士試験に関する情報をまとめた表を作成しました。
| 項目 | 内容 |
| 費用 | – 受験料:15,000円 – 教材費用:数千円~数万円程度 – 講座受講料(任意):数万円~数十万円程度 |
| 学習時間 | – 必要学習時間:800~1,000時間 – 1日3時間の学習で、約9~11ヶ月が目安 |
| 試験内容 | – 選択式試験: – 労働基準法及び労働安全衛生法 – 労働者災害補償保険法 – 雇用保険法 – 労務管理その他の労働に関する一般常識 – 社会保険に関する一般常識 – 健康保険法 – 厚生年金保険法 – 国民年金法 –択一式試験: – 上記科目に関する詳細な知識を問う問題 |
| 資格要件 | – 学歴: – 大学、短期大学、高等専門学校等を卒業 – 大学在学中で62単位以上を修得 – 専門学校(専門士)を卒業 –実務経験: – 労働社会保険諸法令に関する事務に3年以上従事 –その他: – 行政書士試験合格者など |
| 得られる知識 | – 労働基準法や労働安全衛生法の理解 – 労災保険や雇用保険の制度と手続き – 健康保険や年金制度の仕組み – 労務管理や人事制度の構築 – 社会保険手続きの実務 |
| 合格率 | – 平均合格率:約6~7%前後 – 令和6年度:6.9% |
社会保険労務士の資格取得は、企業の労務管理や社会保険手続きの専門家として活躍するための第一歩です。特に、人事・労務部門でのキャリアを目指す方や、労働者の権利保護に貢献したい方にとって、有益な資格といえるでしょう。
法務手続きのエキスパート資格:行政書士
行政書士は、法務手続きの専門家として、官公署への許認可申請や契約書の作成など、多岐にわたる業務を行う国家資格です。この資格を取得することで、行政手続きや法律に関する深い知識を身につけ、個人や企業の法的手続きをサポートすることができます。
以下に、行政書士試験に関する情報をまとめた表を作成しました。
| 項目 | 内容 |
| 費用 | – 受験料:10,400円 – 教材費用:数千円~数万円程度 – 講座受講料(任意):数万円~数十万円程度 |
| 学習時間 | – 必要学習時間:600~1,000時間 – 1日2~3時間の学習で、約10~12ヶ月が目安 |
| 試験内容 | – 法令等科目: – 基礎法学 – 憲法 – 民法 – 行政法 – 商法・会社法 –一般知識等科目: – 政治・経済・社会 – 情報通信・個人情報保護 – 文章理解 –出題形式: – 五肢択一式(4点×40問) – 多肢選択式(8点×3問) – 記述式(20点×3問) |
| 資格要件 | – 受験資格:特になし – 年齢、学歴、国籍を問わず受験可能 |
| 得られる知識 | – 行政手続法や民法などの法律知識 – 官公署への許認可申請手続き – 契約書や遺言書の作成 – 企業法務や国際業務のサポート |
| 合格率 | – 平均合格率:約10~15%前後 – 2023年度:13.98% |
行政書士の資格取得は、法務手続きの専門家として活躍するための第一歩です。特に、法律に関する知識を深めたい方や、個人や企業の法的手続きを支援したいと考えている方にとって、有益な資格といえるでしょう。
電気設備の技術者になれる資格:第二種電気工事士
第二種電気工事士は、一般住宅や小規模な店舗などの電気設備の工事・修理・保守を行うための国家資格です。この資格を取得することで、電気工事に関する基本的な知識と技能を身につけ、電気設備の安全性と機能性を確保する役割を担うことができます。
以下に、第二種電気工事士試験に関する情報をまとめた表を作成しました。
| 項目 | 内容 |
| 費用 | – 受験料:9,300円 – 教材費用:数千円程度 – 講座受講料(任意):数万円程度 |
| 学習時間 | – 電気の基礎知識がある方:50~100時間 – 初学者:100~200時間 – 1日2時間の学習で、約1~3ヶ月が目安 |
| 試験内容 | – 学科試験: – 電気に関する基礎理論 – 配線設計 – 電気機器・配線器具 – 電気工事の施工方法 – 配線図の読み取り – 電気関連法規 –技能試験: – 電線の接続 – 配線工事 – 電気機器・配線器具の設置 – 接地工事 – 配線図に基づく作業 |
| 資格要件 | – 受験資格:特になし – 年齢や学歴に関係なく受験可能 |
| 得られる知識 | – 電気の基礎理論 – 配線設計と施工方法 – 電気機器や配線器具の特性と使用方法 – 電気関連法規の理解 – 安全な電気工事の実践技術 |
| 合格率 | – 学科試験:平均60.6% – 技能試験:平均70.9% |
第二種電気工事士の資格取得は、電気工事業界への第一歩として非常に有益です。特に、電気設備の設計や施工、保守に携わりたいと考えている方にとって、基礎的な知識と技能を証明する重要な資格といえるでしょう。
危険物管理の専門資格:危険物取扱者(乙種)
危険物取扱者(乙種)は、消防法で定められた危険物のうち、特定の類に属する物質を取り扱うための国家資格です。この資格を取得することで、危険物の性質や関連法令、火災予防および消火方法に関する専門知識を身につけ、適切な管理と安全な取り扱いが可能になります。
以下に、危険物取扱者(乙種)試験に関する情報をまとめた表を作成しました。
| 項目 | 内容 |
| 費用 | – 受験料:4,500円前後(都道府県により異なる) – 教材費用:数千円程度 – 講座受講料(任意):数万円程度 |
| 学習時間 | – 必要学習時間:50~100時間 – 1日2時間の学習で、約1~2ヶ月が目安 |
| 試験内容 | – 危険物に関する法令:15問 –基礎的な物理学及び基礎的な化学:10問 –危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法:10問 |
| 資格要件 | – 受験資格:特になし – 年齢や学歴に関係なく受験可能 |
| 得られる知識 | – 危険物に関する法令の理解 – 危険物の性質と分類 – 火災予防策と消火方法 – 基礎的な物理・化学の知識 |
| 合格率 | – 第4類(引火性液体):約30%前後 – その他の類:60~70%前後 |
危険物取扱者(乙種)の資格取得は、危険物を取り扱う業務に従事する際の安全管理能力の証明となり、就職や転職において有利に働くことがあります。特に、化学工場やガソリンスタンド、塗料販売店など、危険物を扱う業種でのキャリアを目指す方にとって、有益な資格といえるでしょう。
快適な住環境を支えるマンション管理の資格:マンション管理士・管理業務主任者
マンション管理士と管理業務主任者は、マンションの適切な管理と運営を支える専門資格です。これらの資格を取得することで、マンション管理に関する法令や実務、設備に関する深い知識を身につけ、管理組合や管理会社のサポートを行うことができます。
以下に、マンション管理士と管理業務主任者の試験に関する情報をまとめた表を作成しました。
| 項目 | マンション管理士 | 管理業務主任者 |
| 費用 | – 受験料:9,400円 – 教材費用:数千円~数万円程度 – 講座受講料(任意):数万円~数十万円程度 | – 受験料:8,900円 – 教材費用:数千円~数万円程度 – 講座受講料(任意):数万円~数十万円程度 |
| 学習時間 | – 必要学習時間:400~500時間 – 1日2時間の学習で、約6~8ヶ月が目安 | – 必要学習時間:300時間 – 1日2時間の学習で、約5ヶ月が目安 |
| 試験内容 | – 出題科目: – 区分所有法等の法令に関する科目 – 管理組合の運営に関する科目 – 建築基準法等・建築設備に関する科目 – マンション管理適正化法に関する科目 –出題形式: – 四肢択一式50問 – 試験時間:2時間 | – 出題科目: – 管理事務の委託契約に関すること – 管理事務の実施に関すること – 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること – 建物及び附属設備の維持または修繕に関する企画又は実施の調整に関すること – マンションの管理に関する法令及び実務に関すること – 出題形式: – 四肢択一式50問 – 試験時間:2時間 |
| 資格要件 | – 受験資格:特になし – 年齢や学歴に関係なく受験可能 | – 受験資格:特になし – 年齢や学歴に関係なく受験可能 – ただし、登録時に2年以上の実務経験が必要 |
| 得られる知識 | – マンション管理に関する法令知識- 管理組合の運営方法 – 建築設備の基礎知識 – マンション管理適正化法の理解 | – 管理事務の委託契約や実施に関する知識 – 管理組合の会計や出納に関する知識 – 建物および附属設備の維持・修繕に関する知識 – マンション管理に関する法令および実務の理解 |
| 合格率 | – 平均合格率:約8~13%前後 | – 平均合格率:約20%前後 |
マンション管理士と管理業務主任者の資格取得は、マンション管理の専門家として活躍するための重要なステップです。特に、マンションの管理や運営に深く関わりたいと考えている方にとって、有益な資格といえるでしょう。
社会人が資格の勉強時間を捻出できない5つの理由

それでは次に、社会人が資格の勉強時間を捻出できない5つの理由を紹介します。
- 本業で疲れて勉強できない
- モチベーションが維持できない
- 家事・育児で忙しい
- 家だと集中できない
- 目標と計画があいまい
それぞれ詳しく解説します。
本業で疲れて勉強できない
本業で疲れたことが原因で、資格の勉強時間を捻出できない方も多いでしょう。どれだけ「資格を取りたい」という強い気持ちがあったとしても、ヘトヘトで帰ってきて、そこから教科書を開くのは難しいですよね。
もし、本当に忙しくて時間が一切捻出できないのであれば、転職や休職という手段も検討すべきです。
ただし、少しでも甘えていると思うのであれば、後ほど紹介する方法を試すことで、解決できる場合があります。
モチベーションが維持できない
最初は「絶対に資格を取得するんだ」と熱い気持ちがあったとしても、数カ月学習してその気持ちが冷めてしまうこともあります。
「何のために勉強しているんだ」もしくは「ある程度知識が身について満足してしまった」という気持ちになった方もいるでしょう。
前者の場合は目標を見失っている可能性があり、当初の目標を再確認することで解決できる場合があります。
後者の場合は、せっかく身に着けた知識が客観的に示せない事実を理解すると「ここまでやってきた学習が無駄になる」と目を覚ますかもしれません。
現在の状況を確認し、自分のモチベーションがない理由を細かく分解して理解できているかを再確認する必要があるでしょう。
家事・育児で忙しい
家事や育児で日々忙殺されている方にとっても、資格取得は難しいですよね。特に、小さいお子さんを育てている方であれば、子どもが泣き出すタイミングがわからず、常に目を光らせていなければならない状況なので、資格勉強に集中できません。
そういった方でもスキマ時間を使った勉強であれば、問題なく進められます。単語帳を使って知識を定着させるなど、忙しさの中でも学習を進められるような工夫が必要です。
家だと集中できない
家だと集中できない場合は、環境を整えることが肝心です。作業環境が散らかっていると、モチベーションや気持ちにも影響が出てしまい、集中力を持続させることが難しくなります。
まずは自分がどんな部屋だと集中できるのかを理解するために、参考画像を用意したり、紙に書いたりしながら必要な道具をそろえていきましょう。
また、家では集中できない場合には、カフェを使って勉強する方法もあります。カフェは500円程度の費用が掛かるので、最初のきっかけとして活用し、そこから家でも集中できるような仕組みを作っていくことが大切です。
目標と計画があいまい
目標と計画があいまいな場合には、どの様に進めればよいかがわからないため、資格勉強に集中できないことがあります。
たとえば、漠然と「〇月までに資格を取りたい」と目標を立てていたとしても、そのために何をすべきなのかを考えられていなければ、今何をすべきかがわからないので、うまく進みませんよね。
目標を達成するために、どのような計画で進めて行くか、細かい部分までしっかりと計算し、そのマイルストーンに従って学習を進めて行く必要があります。
社会人が資格の勉強時間を生み出す4つの方法

最後に、社会人が資格の勉強時間を生み出す4つの方法を紹介します。
- 目標を明確にする
- 休憩時間を削る
- 勉強しなければならない仕組みを作る
- 勉強する場所を用意する
それぞれ詳しく解説します。
目標を明確にする
目標を明確にして学習を効率よく進めて行きましょう。目標を設定する際には、以下3つの観点で考えることが重要です。
- What:何が目標か
- When:いつ達成するのか
- Why:なぜその目標を達成すべきか
また「資格のミカタ」では、目標達成のために使える「資格が取れる!ミカタ手帳」を提供しており、そちらでは以下のように目標を設定するよう設計しています。
- 目標
- 学習記録の設定
- 毎日の振り返り
- 明日の準備
- 継続記録
「資格が取れる!ミカタ手帳」では「計画→実行→振り返り→改善」のサイクルを毎日繰り返せること。小さな成功体験を積み重ねながら、確実に目標に近づいていける設計になっています。
特に大切なのが「振り返り」と「明日の準備」。その日うまくいったことを記録して、次の日に活かせる。「明日は◯時から、◯◯の場所で始める!」と決めることで、実際に行動に移しやすくなります。

まるで「自分専属の学習コーチ」がいるような感覚で、モチベーションを保ちながら学習を続けられるフォーマットを用意しています。
休憩時間を削る
「資格を取る」という新たな挑戦をするためには、これまでに行ってきた習慣を削らなければなりません。特に「休憩時間」と考えられるような以下の時間の使い方は、できる限り削減することが重要になります。
- SNSチェック
- YouTube視聴
- 食後のくつろぎ時間
- TVの視聴
全て削減して、楽しみのない人生にする必要はありませんが、少しずつ削減していかなければ、1日24時間という限りある時間の中で、追加で資格を取ることは困難です。
覚悟を決めて休憩時間を削りましょう。ちなみに、「資格が取れる!ミカタ手帳」の役立ちコンテンツでは、以下のような情報をお伝えしています。
ここまで設定すれば、あとは資格の勉強をするだけです。
と言いたいところですが、習慣化はそんなに簡単なことではありません。これまでの習慣を変えて新たなことに挑戦するのは大きなストレスがかかってしまうからです。
そして「楽をしたい」という誘惑によっても資格の勉強が疎かになるケースがあります。
資格取得には「新しい時間」が必要です。しかし、私たちの1日は24時間と決まっています。つまり、「新しい時間を生み出す」ためには、「何かを手放す」必要があります。
そこで、「成功への覚悟 – 習慣改革ワークシート」を使いましょう。
習慣改革が資格取得の成功を決める
資格取得の成功には、新しい習慣を始めるだけでなく、いくつかの習慣を「手放す勇気」が必要です。なぜなら、私たちの1日は24時間と決まっているからです。新しい時間を生み出すためには、必然的に何かを手放さなければなりません。
見えない時間を可視化する
多くの人は「時間がない」と感じています。しかし、本当に時間がないのでしょうか?
SNSでの無駄なスクロール、動画視聴での「あと1本だけ」の連続、何となくスマートフォンを触る時間…。これらの「見えない時間」を数値化することで、使える時間が明確になります。
例えば
- SNSを1日2時間減らすと → 月60時間の学習時間
- 夜の動画視聴を1時間減らすと → 月30時間の学習時間
- だらだらスマホを30分減らすと → 月15時間の学習時間
単に「やめる」だけでは長続きしません。やめるための具体策を取り入れることが重要です。
勉強しなければならない仕組みを作る
仕組み作りも重要なポイントです。

今日は疲れたからやらない

明日リフレッシュした状態で作業をした方が効率いいよな
と、自分の都合の良い解釈で勉強を疎かにしてしまうケースもありますよね。
しかし「明日やろうは、ばかやろう。」毎日勉強しなければ、資格取得から少しずつ遠ざかってしまいます。
勉強しなければならない仕組みを作る方法として、以下について考えるのがおすすめです。
- 場所:
- 準備物:
- リマインダー設定:
- 障害となりそうなこと:
- 対策:
明日学習を確実に始めるための仕組み
この仕組みを取り入れ、どれだけ疲れていても必ず学習できる環境を整えておきましょう。

僕は、枕の上に教科書を開いて置いて、寝れない状態を作っていました!
勉強する場所を用意する
勉強する場所を用意することもおすすめの方法です。リビングや自分の机で学習を進めてもなかなか集中できないという場合には、少しだけそこから離れることで、集中できるケースがあります。
たとえば、普段は学習机を前にして、ワークチェアに座って作業をしている方は、ローテーブル位の高さの机で作業をすると気分が変わって集中しやすいかもしれません。
また、休日には必ず図書館へ行き、1週間のうち2日間は環境を変えて勉強することで、気分転換になり、自宅でも作業ができるようになるかもしれません。
場所を変えるのはおすすめのアプローチなので、ぜひ試してみてください。

僕はカフェで作業をする際に、雨の環境音を流し勉強しています。この音が流れる集中できるようになったので、現在は自宅でもこの音楽を流しながら勉強をすることで、集中できています。
まとめ

この記事では、忙しい社会人でも勉強時間を確保する方法について解説しました。 忙しくて集中ができない場合には、結論、毎日学習できる仕組みを作り、自分でも取れそうな資格を選択することが大切です。
また、勉強時間が確保できない社会人でも比較的取りやすい資格も紹介しました。
ぜひ、今回の内容も参考に資格取得の挑戦をあきらめず、キャリアアップを目指してみてくださいね。
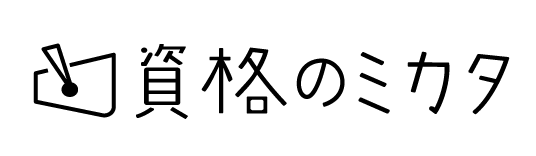




コメント