資格の勉強で、ノートを使う時、以下のような課題を感じたことはありませんか?

ノートの取り方は合ってるのかな?

綺麗にノートを取ったのに、全然覚えられない!

ノートがうまくまとめられない…
多くの方が課題を感じているとはいえ、解決策が見つからないと悩む方は多いでしょう。
今回は、効率よく資格勉強ができるようなノートの作り方について、解説していきます。
ノート作りに失敗してしまうと、これからの学習効率が少しずつ低下してしまい、最悪の場合、資格を取得できない可能性があります。
すぐに使える内容を具体的にお伝えするので、ぜひ活用して、簡単に楽に覚えられるような最強ノートを作りましょう。
資格勉強の効率が変わる!ノート選びの基準

ノート選びは資格取得に大きな影響を与えるといっても過言ではありません。
勉強スタイルに合わせ使いやすいノートを選ぶことで、復習や見直しがスムーズになります。ポイントを2つ見ていきましょう。
- 用途別おすすめのノートの選び方
- サイズと罫線の選び方
用途別おすすめのノートの選び方
資格によって勉強に最適なノートは異なります。
各資格で必要な知識の性質や記録方法が違うため、、最適なノートの特徴も変わってくるからです。
- 法律系の資格:インデックスが付けられるノート⇒条文や判例が整理しやすい
- 技術系の資格:方眼罫のノート⇒図や表が描きやすい

このように、資格の特性に合わせたノート選びが大切になります。
複数科目を同時に学習する場合は、科目ごとに色分けされたノートを使うことで、効率的な学習が可能になります。
サイズと罫線の選び方
前項よりも、さらに具体的な用途別のおすすめのノートの選び方をまとめました。
| 会計系資格(簿記、FP、税理士など) | ・B5サイズの6㎜罫線ノート ・ルーズリーフタイプ | ・計算式や数字を書くのに適した行間 ・仕訳や財務諸表を書きやすい余白設計 ・項目ごとに差し替えや並べ替えが可能 ・練習問題の解答を別保管できる |
| 語学系資格(TOEIC、英検など) | ・A5サイズの単語帳タイプ ・スパイラルノート | ・持ち運びやすく隙間時間の学習に最適 ・見開きページで単語と意味の整理ができる ・平らに開いて書きやすい ・リスニング問題の書き取りがスムーズ |
| 医療系資格(看護師、薬剤師など) | ・B5サイズのマルチカラーノート ・インデックス付きノート | ・人体の図や化学式を色分けして記録 ・重要度に応じて色分け管理が可能 ・体系や症例ごとに素早く参照可能 ・複数の科目を効率的に管理できる |
| 国家資格(行政書士、司法書士など) | ・A4サイズの縦型ノート ・仕切り付きノート | ・条文や判例を余裕を持って書き込める ・資料との照合がしやすい ・分野別に整理しやすい ・過去問と解説を関連付けて保管できる |
| IT系資格(基本情報、応用情報など) | ・B5サイズの方眼ノート ・タブ付きノート | ・フローチャートやER図を正確に描ける ・プログラムのインデントを揃えやすい ・言語別やシステム別の区分けが容易 ・アルゴリズムと実装を関連付けて整理できる |
これらの特徴を組み合わせることで、より効率的な資格勉強を進めることができるでしょう。学習の進度や理解度に応じて、適宜ノートの使い方を調整していくことをおすすめします。
記憶に残る!効率的な資格勉強のノートの書き方

ノートを一生懸命まとめたのに

覚えられない!
と感じたことはありませんか?
実は少しの工夫で見やすく、記憶に残りやすいノートに仕上がります。
ここでは、4項目にわけて解説します。
3色を使い分けてノートを取る
色を使い分けてノートをとることで、記憶が定着しやすくなります。
3色を使い分けてノートを取る際の具体的な手順は、以下の通りです。
- 黒ペン:講義内容や教科書の要点、基本的な定義や概念、計算式の基本形
- 赤ペン:試よく出題される項目、覚えるべき公式や用語、間違いやすい部分への注意喚起
- 青ペン:具体例や応用例、関連する参考情報、自分なりの解釈やメモ
ポイントは、各色の役割を一貫させることです。自分の好きな3色を選んで書くと、モチベーションも上がり、学習を効率化できるはずです。
色の意味を固定することで、後から見返したときに情報の重要度が一目でわかり、効率的な復習が可能になります。時間をかけて丁寧に書くよりも、素早く正確に情報を整理することを心がけましょう。
図解や記号を使い見やすくまとめる
図解や記号を使い、見やすくまとめることで、情報を素早く思い出しやすくなります。
基本的な図解記号
| 矢印(→) | 因果関係や手順の流れを書く |
| 波線(~) | 言い換えや補足説明する |
| 四角囲み(□) | 重要な用語や定義を囲む |
| 丸囲み(○) | キーワードやポイントを囲む |
| アスタリスク、米印(*、※) | 注意点や例外事項がある時に書く |
図解の活用方法

図解の活用方法について詳しく知りたい方は、以下のボックスを開いてご確認ください!
頭の中のアイデアや知識を放射状に広がる図で表現する整理方法です。中心に主要テーマを置き、そこから枝のように関連する情報を次々と広げていきます。
マインドマップの基本的な作り方をまとめてみました。
1、中心テーマの設定をする | ・用紙の中央に主要なテーマを書く・テーマを囲んで協調する・できるだけ具体的な言葉を選ぶ |
2、メインブランチの作成 | ・中心から太い線で主要な項目を放射状に配置する・異なる色を使って分類する・キーワードは線の上に配置する |
3、サブブランチの展開 | ・メインブランチから細い線で詳細項目を広げる・関連する情報を自由に追加する・図やイラストも活用する |
マインドマップを活用する時は、以下のポイントをおさえましょう。
- シンプルな単語を使用する
- 矢印や記号で関連性を表現する。
- 定期的に更新や追記を行う。
このようにマインドマップを段階的に書き進めると、内容の全体像を把握しやすくなります。そして、情報の関連性が図として表されるため、記憶が定着にも役立つでしょう。
フローチャートは、作業の手順や判断の流れを図や記号を使って表現する方法です。作業の開始から終了まで、矢印でつないだ図形を使うことで、手順が見やすくなります。
基本的に図形と矢印を組み合わせて作成します。
主に使用する図形は以下の通りです。
- 楕円:開始と終了点を書く
- 長方形:処理や作業を書く
- ひし形:条件による分岐を書く
- 平行四辺形:データの入出力を書く
記号の使い方と活用例は以下の通りです。
記号の使い方 | ・矢印は処理の流れを示す・分岐は「Yes/No」で表現する・処理は簡潔な言葉で書く・複数の処理がある場合は上から下へ配置する |
活用例 | ・プログラムのアルゴリズム設計・業務手順の可視化・トラブル対応の手順書・意思決定プロセスの図示 |
このように手順や判断の流れを図で示すことで、複雑な処理もわかりやすくなりミスの防止にも役立ちます。
表を効果的に活用するための3つの方法を紹介します。
■比較型の表
「簿記の資産と負債」の比較を具体例として挙げます。
| 項目 | 資産 | 負債 |
| 性質 | 経済的価値がある | 将来の支払義務 |
| 貸借 | 借方(左側) | 貸方(右側) |
| 増加 | 借方に記入 | 貸方に記入 |
このように項目を縦軸、比較対象を横軸に配置し、類似点と相違点を明確に区別して書きます。
また、重要な違いは、色や記号で強調すると見やすいでしょう。
■分類型の表
「ITパスポートのセキュリティ対策」を具体例として挙げます。
| 対策区分 | 具体例 | 主な効果 |
| 物理的対策 | 入退室管理 | 不正アクセス防止 |
| 技術的対策 | パスワード設定 | データ保護 |
| 人的対策 | 教育研修 | 意識向上 |
上記のように、大分類を行に、詳細を列に書きます。関連する項目をグループ化し、下層から上層に順に積み重ねて、全体を構成している階層構造を意識した配置にするとよいでしょう。
■手順型の表
手順型の表は、複雑な作業工程を整理し、学習時や実務時のチェックリストとして活用できます。表の各項目は簡潔に書き、必要に応じて詳細な解説を加えることでより効果的に学習できるでしょう。
「MOS資格」を具体例として挙げます。
| 手順 | 学習内容 |
|---|---|
| ワークシートとブックの管理 | ワークシートの作成、フォーマット設定、ブックの共有と保護 |
| セルと範囲の管理 | セルの書式設定、データの入力規則、条件付き書式の適用 |
| テーブルの作成 | テーブルの作成、並べ替え、フィルターの適用 |
| 数式と関数の使用 | 基本的な関数(SUM、AVERAGE等)や論理関数(IF、VLOOKUP等)の活用 |
| グラフの作成 | グラフの挿入、種類変更、書式設定 |
| オブジェクトの管理 | 画像や図形の挿入、編集、配置 |
手順型の表を書くときのポイントを以下にまとめました。
- 時系列や順序で整理をする
- 各ステップの要点を簡潔に記載する
- チェックポイントを明記する
紹介した3種類の表は、復習時に素早く情報を確認できる利点があります。ただし、情報は必要最小限に抑えて、見やすさを重視しましょう。
また、定期的に内容を更新し、勉強の進み具合に合わせて表を発展させることで、より効果的な学習ツールになります。
階層図は、情報の上下関係やある集合が他の集合の部分集合である関係を指す、包含関係を見やすく表現する方法です。
組織図のように、上位の概念から下位の概念へ、枝分かれしていく構造で表現します。
階層図の作り方について例をまとめました。
■基本構造
最上位概念
├── 上位概念A
│ ├── 中位概念A1
│ └── 中位概念A2
└── 上位概念B
├── 中位概念B1
└── 中位概念B2
■活用例:ITシステムの構成
情報システム
├── ハードウェア
│ ├── サーバー
│ └── クライアント
└── ソフトウェア
├── OS
└── アプリケーション
このように、情報を階層的に整理することで、全体像の把握と詳細の理解が同時にできます。
勉強する時は、上位の概念から順に理解を深め、徐々に詳細な内容に進むことで、効率的に学習できるでしょう。また、定期的に全体を見直すことで、知識の整理と定着が図れます。
整理のルールを決める
統一されたルールに従ってノートを作成することで、書いた内容が見やすくなります。
IT資格の学習を例に挙げてみます。
- 用語の定義:青枠で囲む
- 計算式:赤枠で強調する

上記のように統一したルールを決めることで、復習する時に便利です。
最初にしっかりとしたルールを決めて、途中で大きく変更せずに守り続けることで、効率的に学習することができます。
学習を進める中で微調整が必要な場合は、変更点をメモしておくとよいでしょう。
コーネル式ノート術を活用する
コーネル式ノート術は、ノートのページを3つのエリアに分けて情報を整理する効果的な方法です。
キーワードと要点、詳細な内容、要約をまとめて記入することで、学習内容の整理と復習を効率的に行えます。
ページの構成の仕方をまとめてみました。
| キューエリア(左側:6㎝程度の幅) | ・キーワードを書く ・重要な用語を書く ・試験頻出ポイントを書く ・確認問題を書く |
| メインエリア(右側:14㎝程度の幅) | ・講義内容の詳細を書く ・図や表を書く ・計算式を書く ・具体例を書く |
| サマリーエリア(下側:5㎝程度の幅) | ・その日の学習のまとめを書く ・重要ポイントの要約を書く ・次回の学習目標を書く |
コーネル式は、後から復習しやすい点が特徴です。

キューエリアを隠して内容を思い出したり、サマリーだけを読んで要点を確認したり、様々な方法で復習できるでしょう。
定期的に復習すると、記憶の定着度が高まり、効率的な試験対策が可能になります。
【目的別】資格勉強がはかどるノートの使い分け方

資格勉強では、目的に応じてノートを使い分けることで、学習効率が大きく向上します。特に新しい知識を吸収する「インプット」の段階では、情報を整理し、理解を深めるための専用ノートが効果的です。
インプット用ノート
教科書や講義の内容を自分の言葉で整理し、理解を深めたい場合にはインプット用のノートを作りましょう。
基本的なノートの構成
- 見開き左ページ:教科書やテキストの要点を書く
- 見開き右ページ:自分なりの解釈や補足説明を書く
- 余白:関連する用語や参照ページを書く
記載内容の種類
- 定義:用語の正確な意味を示す
- 公式:計算方法や原則を書く
- 図解:概念の視覚化を示す
- 具体例:実務での応用例を書く
活用方法について、簿記検定を具体例として取りあげます。
- 左のページに仕訳のルールを書く
- 右ページに具体的な取引例を記録する
このように、教科書の内容をただ写すのではなく、自分の理解度に合わせて書き、再構築することで、より深い理解につながります。
特に、初めて学ぶ人は、基礎概念をしっかり理解することが重要なため、丁寧にインプットノートを作成するといいでしょう。
暗記用ノート
暗記用ノートは、資格試験の重要項目を効率的に記憶するための専用ノートです。
通常のノートとは異なり、情報を隠して確認でき、繰り返し復習できるような仕組みを持ちます。。暗記したい内容を「問題と解答」の形式で整理できる点が、最大の特徴です。
具体例をまとめてみました。
- 英語資格:単語とその活用例を見開きで書く⇒フラップ形式で隠せるようにする
- 法律の資格:条文の要点と具体的な判例を並べて書く⇒理解と暗記を同時に進める
- IT資格:技術用語の定義と実務での使用例を並べて書く⇒セキュリティ対策は、チェックリスト形式にして項目漏れを防ぐ
1ページあたりの情報量を調節し、短時間で集中的に暗記できる構成にすることで、試験対策に効果的です。
間違い克服ノート
間違い克服ノートは、自分の苦手分野や間違いやすいポイントを集中的に管理するための専用ノートです。間違いの原因分析と対策の記録を組み合わせて書くことで、なぜ間違えたのか、どうすれば正解できるのかを整理します。
間違い克服ノートを効果的に活用するための構成をまとめました。
- 見開き左ページ:間違えた問題、内容、理由の分析を書く
- 見開き右ページ:正しい解答方法、類似問題のパターン、間違い再発防止のポイントを書く
このように、単に間違いを記録するだけでなく、その克服方法までを含めて整理することで、効率的に弱点の克服ができるでしょう。
ノートの取り方でよくあるNG例とその対処法
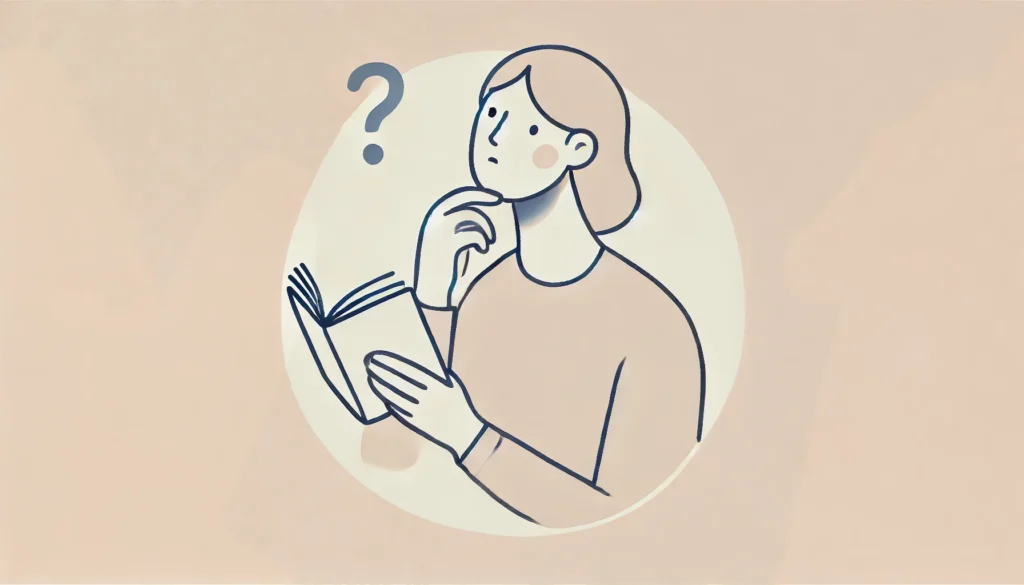
ノートを取るだけで時間がかかってしまったり、内容を覚えてなかったりする経験はありませんか?

せっかくなら効率よくノートを取り、絶対に試験に合格したいですよね。
ここでは、多くの人がやりがちなNG例をまとめたので、対処法を理解し、無駄を省きましょう。
1枚に多くのことを書きすぎてしまう
1枚のページに多くの情報を詰め込みすぎると、重要なポイントがわからなくなり、復習する時に効率が低下してしまいます。
この問題を解決するために、効果的な工夫をまとめました。
| 情報の適切な分量 | ・1ページにつき1テーマにする ・余白を30%程度確保する ・図や表は簡潔にする |
| 分割のポイント | ・関連する内容ごとにページを分ける ・見開きで情報が完結するように意識して書く ・補足は別のページに書く |
このように整理をしてノートを取ってみましょう。
情報量の目安としては、後から見返したときに3分以内で内容を把握できる状態が適切です。これより多い場合は、項目を分割して別のページに書くことをおすすめします。
綺麗に書くことに時間をかけてしまう
ノートを綺麗に書くことにこだわりすぎると、本来の目的である知識の習得や理解に時間を割けなくなってしまいます。
効率的なノート作りのためのポイントをまとめました。
| 情報の記録に重点をおく | ・重要なキーワードを優先する ・箇条書きを活用する ・図解は最小限の情報にする |
| 時間配分の目安 | ・講義や教材1ページにつき3分以内にする ・図解作成は5分以内にする ・色分けは3色までにする |
| 効率化のコツ | ・記号や略語を活用する ・余白を活用して追記する ・付箋を使った補足をする |
大切なのは見た目の美しさではなく、内容の正確さと理解のしやすさです。時間をかけすぎないよう、1つの項目の記入時間を決めて、その中で完結させることを心がけましょう。

綺麗に書くことよりも、必要な情報を素早く記録し、復習時に活用できる形に整えることが重要です。
何も考えずに書き写してしまう
教科書やテキストの内容を何も考えずにそのまま写すと、学習の意味がありません。
学習効率を上げるノート作りのために、以下のポイントに注意しましょう。
| 内容を咀嚼する | ・要点を自分の言葉で言い換える ・具体例を考えて追記する ・実務での活用場面を想定する |
| 理解を深める工夫をする | ・図や表で関連性を整理する ・なぜそうなのか理由を考える ・他の概念との違いを比較する |
| アウトプットの準備をする | ・説明できる形に整理する ・重要なポイントに印をつける ・疑問点を明確にメモする |
単に写すのではなく、内容を理解しながらノートを取ることで、試験対策だけでなく、実践的な知識として身につけることができます。
テキストを読みながら「なぜ?」「どうして?」と考える習慣をつけ、疑問点がある場合は、必ずその場で解決するようにしましょう。
資格ごとに分けずノートを使ってしまう
複数の資格の勉強内容を1冊のノートに混ぜて書くことは、復習時の効率を大きく下げる原因となります。
内容が混在することで、理解が難しくなったり、試験直前の見直しに時間が掛かったりするからです。
効率的なノート管理のために、おすすめの分類方法を以下にまとめました。
資格別の分類 | ・資格ごとに専用ノートを使う ・表紙に資格名と学習期間を書く ・インデックスで科目を区分けする |
科目別の整理 | ・科目ごとにセクション分けする ・関連する過去問をまとめる ・練習問題の解答を別冊に書く |
活用のポイント | ・色分けで資格を区別する ・進捗状況を表紙に記録する ・復習計画を立てやすくする |
このように、資格や科目ごとに明確に分けることで、学習の進捗管理がしやすくなり、効率的に復習ができます。
特に、複数の資格を同時に学習する場合は、ノートの使い分けを徹底し、各資格ごとの学習スタイルを確立するとよいでしょう。
資格勉強でノートと一緒に活用するのがおすすめのデジタルツール
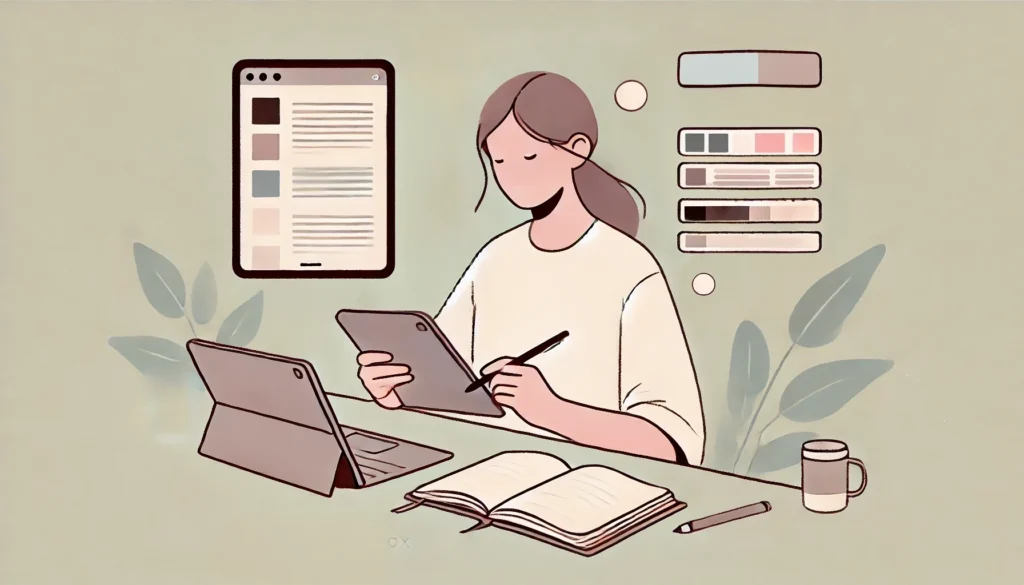
ここまで、ノートの取り方や学習の仕方について説明してきました。
ノートのみで勉強するよりも、一緒に活用することで、より効率的になり、勉強がはかどるデジタルツールをご紹介します。
バレットジャーナルを活用する
バレットジャーナルとは、シンプルな記号と箇条書きを使い、タスクや予定、メモを管理する手帳システムです。
「・」(箇条点)、「×」(完了)、「>」(移動)、「○」(予定)といった基本的な記号を組み合わせて情報を整理します。
ノートの学習と合わせて、スマートフォンやタブレットでバレットジャーナルのアプリを活用することで、学習計画と進捗状況がわかりやすくなります。
バレットジャーナルの効果的な活用方法を以下にまとめました。
| 月間スケジュール管理 | ・学習目標の設定をする ・試験日程の記録をする ・復習のタイミングを計画する |
| 週間タスク管理 | ・科目ごとの学習時間配分を書く ・問題演習の進捗状況を書く ・弱点分野の克服計画を書く |
| 日々の記録 | ・学習内容のチェックリストを書く ・理解度の自己評価を書く ・要復習ポイントのメモをする |
| 活用のポイント | ・シンプルな記号で状態を表現する ・重要度に応じて色分けをする ・定期的な振り返りを実施する |
手書きノートと併用することで、アナログとデジタルそれぞれのメリットを活かした学習管理ができます。
特に複数の資格を同時に学習する場合は、進捗状況の配分と時間配分の最適化に役立つでしょう。
同時並行で資格を取得したい方は、以下の記事をご覧ください。
時間管理アプリを活用する
時間管理アプリは、学習時間の記録や進捗管理を自動化できるデジタルツールです。
学習内容や時間を入力すると、グラフや統計データとして記録され、学習の傾向や効率を分析できます。
時間管理アプリの効果的な活用方法は以下の通りです。
| 学習記録の管理 | ・科目ごとの学習時間を書く ・学習内容のタグ付けをする ・理解度の評価をする |
| 進捗状況の分析 | ・月間学習時間の推移がわかる ・科目別の時間配分がわかる ・目標達成率の確認できる |
| モチベーションの維持 | ・継続日数の記録をする ・学習仲間との共有できる ・目標達成の可視化ができる |
| データの活用法 | ・効率のよい時間帯の特定をする ・弱点分野の把握をする ・学習計画の最適化をする |
このように時間管理アプリを活用することで、効率的に管理ができます。特に長期的な学習が必要な資格試験では、継続的なモチベーションの維持と時間管理に役立ちます。
また、アプリのコミュニティ機能を活用することで、同じ目標を持つ仲間との情報交換や励まし合いも可能です。

1人では維持が難しい学習のモチベーションを高く保てるでしょう。
時間管理アプリについては、以下の記事で詳しく解説しています。
YouTube動画を活用して勉強する
YouTube動画は、資格勉強に関連する動画もたくさんあり、学習効果を高める強力なツールですが、ただ視聴するだけではあまり効果が期待できません。
ノートと組み合わせた効果的な学習のために、以下のポイントを意識しましょう。
視聴前の準備 | ・学習テーマの確認をする ・関連する教科書のページを用意する ・ノートの見開きページを確保する |
視聴中の作業 | ・キーワードをメモする ・図やフローチャートを模写する ・重要な説明を箇条書きする ・タイムスタンプ(動画の特定の時間位置を示す目印)を記録する |
視聴後の整理 | ・メモを体系的に再構成する ・教科書との対応を確認する ・疑問点を書き出す ・要復習ポイントをマークする |
このように、視聴だけで終わらないように、ノートを取りながら学習を進めることが重要です。

また、定期的に動画の内容を見直せるようにタイムスタンプと共にポイントを記録しておくと便利です。
まとめ

この記事では、資格勉強が効率化できるノートの取り方を理解するために、様々な角度から解説しました。
ノートの取り方でやりがちなNG例は、みなさんも経験があるのではないかと思います。
- 1枚に多くのことを書きすぎてしまう
- 綺麗に書くことに時間をかけてしまう
- 何も考えずに書き写してしまう
このNG例をうまく回避するだけでも、見やすく復習に使えるノートができます。
資格勉強の科目の特性を把握し、図や表をうまく活用することで学習の効率が上がります。
また、ノートだけでなくデジタルツールを活用することで、時間管理や学習効果を高まり、より効率的に勉強を進めることができるでしょう。

ぜひ、本記事の内容を活用して、勉強を進めて資格試験に合格しましょう!
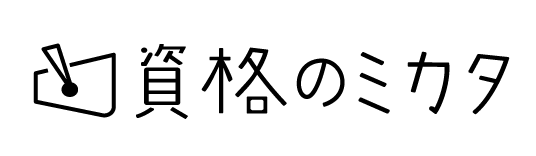





コメント