資格勉強では、限られた時間で最大の効果を得るために、計画の立て方が重要です。
みなさんの中に、試験日までの残り日数を把握せずに勉強を始めてしまい、終盤で「まだ半分も終わっていない!」とパニックになった経験がある人はいませんか?

しっかりとした計画があれば、日々の進捗が見えるので安心感が違います。
例えば、1日30ページと決めておけば、その日のノルマを達成する喜びを味わえるものですよね。また、計画的に学習することで、苦手分野に十分な時間を割り当てられ、バランスよく実力を伸ばせます。
本記事を最後まで読み、実践することで、合格への道しるべとなる計画を立てることができるでしょう。ぜひ参考にしてみてください。
この記事を書いた人

佐藤みき
書道に興味を持った小学校2年生~中学校までの約8年間、習字教室に通い、初等師範免許を取得しました。
書道を習ったことで、集中力・忍耐力・観察力が培われ、日々の生活に役立っています。
その他にも、いろんな資格に興味があり勉強中です。一緒に楽しく学びましょう!
資格勉強の計画を立てる時によくある失敗パターン

いざ計画を立てる時に、ありがちな失敗パターンを3つあげました。

この失敗パターンに当てはまっていないか、確認してみましょう。
具体的な勉強時間を確保していない
多くの人が「時間がある時に勉強すれば良い」と考えがちですが、これは資格試験の最大の落とし穴です。
みなさんは、以下のような経験はありませんか?
- 平日:仕事が終わりに勉強しようと考えていても、残業や急な用事で勉強できない。
- 休日:「時間があるからゆっくり勉強しよう」と思っていても、予定が入ったり疲れて寝てしまったりして、思うように勉強が進まない。
このように具体的な時間を確保せずに勉強を始めると、試験日が近づいてから焦ることになります。
計画的な勉強をするために、まず1週間の中で「いつ」「どのくらいの時間」勉強するのかを明確にすることが大切です。そうすることで、限られた時間を最大限に活用できるようになります。
細かすぎる計画で挫折する
「30分ごとの詳細なスケジュール」や「1日の学習を10個以上の細かいタスクに分割」のように、緻密な計画は学習を難しくします。
細かい時間設定の計画は、予定通りに進まなかったり、理解に時間がかかる単元に遭遇したりすることで、思うように進まない焦りから学習意欲の低下も招く恐れがあります。
計画を立てること自体は重要です。細かい時間設定の代わりに「今週は第3章を終わらせる」といった達成目標を設定してみましょう。その中で柔軟に時間を使うことで、無理なく学習を続けられるはずです。
具体的な目標設定ができていない
資格勉強を始める際に

がんばって勉強する

毎日コツコツ取り組む
といった漠然とした目標を立てていませんか?
このような抽象的な目標設定では、学習の進捗状況を把握することができません。また、進捗状況がわからないため、学習ペースや学習方法が合っているか確認できず、不安だけが募ってしまいます。

具体的な目標設定例をあげます!
- 今週は管理簿記の第4章まで終わらせる
- 毎週50問は過去問を解く
このように達成後を明確に測れる目標を立てましょう。これなら進捗状況を正確に把握でき、必要に応じて学習方法の見直しもできます。
効率的な学習のためには、まず具体的な目標設定から始めることが重要になります。
無理なく続けられる資格勉強の計画手順

失敗パターンを把握したところで、次は具体的な計画の立て方を4つの項目にわけて解説します。
現状分析(利用可能な時間の把握)
効果的な学習計画を立てるには、まず自分の1週間の生活パターンを把握することから始めましょう。平日と休日に分けて、以下の手順で時間を分析することが重要です。
| 固定の予定を書き出す | 仕事/学校の時間 通勤/通学時間 食事の時間 睡眠時間 |
| 生活に必要な時間を確認する | 家事の時間身支度の時間 休憩時間 |
| 学習可能な時間帯をチェックする | 通勤電車の中 休憩時間帰宅後の夜の時間 休日の午前中 |
この分析により、平日は通勤時間と夜の1時間、休日は午前中の2時間といった具合に、具体的な学習可能時間が見えてきます。
無理のない計画を立てるには、まずこの現状把握が重要になります。
必要な学習時間の算出
資格合格に必要な学習時間は、以下の手順で具体的に算出していきます。
| 教材の総ボリュームを確認 | テキストのページ数 問題集の問題数 過去問の数 |
| 1単位あたりの所要時間を測定 | テキスト1ページの読解時間 問題1問の解答時間解説を読む時間 |
上記の内容を把握し、総学習時間の計算をします。計算の仕方は以下の公式に当てはまります。
- 基本学習時間 = 教材量 × 1単位あたりの所要時間
- 復習時間 = 基本学習時間 × 0.3
- 予備時間 = (基本学習時間 + 復習時間) × 0.2
例えば、300ページのテキストで1ページ5分、1000問の問題集で1問3分かかる場合、基本学習時間は75時間になります。
これに復習時間22.5時間、予備時間19.5時間を加えた合計117時間が、合格までに必要な総学習時間の目安になります。
上記の計算方法を参考にし、資格試験までに必要な学習時間を把握しましょう。
週単位での計画立案
週単位で計画を立てることで、日々の予定変更にも柔軟に対応できます。
例えば、平日の学習予定が仕事の残業で予定通りに進まなくても、週末に調整できます。また、その週の目標を「過去問を50問解く」といった具体的に設定することで、達成感も得られやすくなります。
実際に学習を進めていくと、ある単元は予想より早く終わり、別の単元は理解に時間がかかるといった変動が生じます。週単位の計画であれば、そうした学習の進み具合に応じて柔軟に調整できます。

毎週末に次週の計画を立て直すことで、常に最適なペースを保ちながら、着実に目標へと近づいていくことができるのです。
1日の具体的な学習量設定
1日の学習量は「時間」ではなく「具体的な量」で設定していくことがポイントです。以下の手順で無理のない目標を立てましょう。
| 学習量の基準を決める | テキスト:ページ数 問題集:問題数 動画講義:本数 |
| 曜日ごとの目標設定 (平日) | 通勤時間:テキスト2ページ 昼休み:問題5問 帰宅後:動画1本 |
| 曜日ごとの目標設定(休日) | 午前中:テキスト10ページ 午後:問題20問夕方:復習30分 |
| 調整のポイント | 理解度に応じて量を増減 予定変更時は翌日以降に回す 週末は余裕を持たせる |
このように具体的な量で設定することで、その日の達成度が明確になり、モチベーションを維持しやすくなります。
ちなみに、休日に資格勉強をする際のコツはこちらの記事で詳しく紹介しています。
効果的に資格勉強の進捗を管理する方法

計画を立て、実際に勉強を始めると、定期的に進捗状況を把握することが重要になります。計画通りに進んでいるか、学習ペースが合っているか見極めるためのポイントを解説します。
1日の目標は柔軟に調整
目標達成のために重要なのは、現実的な計画立案と柔軟な調整です。

1日の目標達成を柔軟に行うことで、より効果的な進捗管理ができます。
例えば、朝のミーティングで「今日はレポート作成を3件完了させる」と決めても、急な問い合わせ対応が入れば、すぐに目標を見直すことが大切になります。
進捗管理をスムーズに進めるポイントを以下にまとめてみました。
| 目標の優先順位付け | 重要度と緊急度で分類 1日の時間配分を明確化 予備時確保確保 |
| 進捗状況の可視化 | タスク管理ツールの活用 15分単位での記録 チーム内での共有 |
| 振り返りと調整 | 目次での達成度確認 未完了タスクの原因分析 翌日の目標への反映 |
このように段階的に管理することで、効率的な業務遂行が可能になります。進捗に遅れた場合でも、柔軟に対応できる体制を整えることが大切です、
予定通りに進まないことを想定し、調整の余地を残しておくことで、ストレスなく目標達成を目指せます。
週末に進捗確認
週末に進捗確認を行うことで、仕事の質と効率が大きく向上します。平日は目の前の業務に集中しながら、週末にはしっかりと振り返りの時間を確保することで、理想的な進捗管理が実現できます。
例えば、金曜日の午後に30分程度の時間を設けて、その週の成果を確認すると、翌週のスケジュールも立てやすくなります。
週末の進捗確認では、完了した作業を評価するだけでなく、予定より遅れている部分も特定できます。これにより、優先順位の調整や追加の時間確保など、早めに必要な対策を検討できます。
予備日の確保と活用法
予備日の重要な注意点と活用方法を以下のようにまとめました。
予備日の基本的な注意点 | 「後で何とかなる」という考え方は禁物 通常の作業日は予備日がないものとして進める 月末締め切りの場合、26日までを通常作業日として設定する |
予備日の正しい位置づけ | 遅れを取り戻すための時間ではない 作業の品質を高めるための時間 余裕を持って取り組める時間 |
予備日の具体的な時間配分 | 作業の見直し:30%改善点の実施:40%次の工程の準備:30% |
効果的な活用のポイント | 目的を事前に明確にする使い方を具体的に決めておく通常作業日は全力で取り組む予備日は余裕を持って品質向上に充てる |
このように、計画的に予備日を活用することで、効率的な進捗管理ができます。
資格勉強の計画を継続させるコツ

計画を立てても、その通りに継続できなければ意味がありません。
ここでは、計画を継続させるためのコツを3つ解説します。
時間ではなく学習量で目標設定
時間ではなく学習量で目標設定することで、着実な成長を実感できます。
例えば「毎日2時間勉強する」という目標は、その日の体調や予期せぬ用事で達成が難しくなります。一方「英単語を30個覚える」という具体的な量で設定すれば、自分のペースで柔軟に取り組むことができるでしょう。
学習量をベースとした目標設定には、大きな達成感が伴います。時間を気にせず、1つひとつの課題に集中できるため、学習の質も自然と向上します。
週単位での調整を習慣化
週単位での計画調整は、長期的な目標達成への近道となります。日々の予定は突発的な変更が付きものですよね。例えば、月曜日に予定していた学習が急な残業でできなくなっても、週末までに調整する余裕があれば、心理的な負担も軽くなります。

また、週単位での振り返りは、自分の生活リズムを理解する良い機会になります。
平日は夜型の学習が効果的だったり、休日は朝型の方が集中できたりと、曜日ごとの特徴が見えてきます。これらの気づきを週ごとの計画に反映することで、より実践的な目標設定が可能になるでしょう。
週の前半で予定通り進まなかった場合でも、後半で調整できる余地があるため、挫折せずに継続できます。このように柔軟に調整することを習慣化し、長期的な目標を達成させましょう。
無理のないペース配分
無理のないペース配分とは、自分の生活リズムや体力に合わせて学習や作業量を調整することです。確実にこなせる量を設定することで、毎日の目標を達成できる喜びを感じながら、着実に前進することができます。
継続的な成長には、短期的な成果よりも長期的な積み重ねが重要です。特に新しいスキルの習得や大きな目標に向かう場合、無理なく続けられる環境作りが成功への鍵となります。

一時的な頑張りよりも、日々の小さな積み重ねを大切にすることで、確実な進歩を実感できるようになります。
このように、自分のペースを守りながら学習や作業を進めることで、ストレスなく目標達成に向かうことができます。
確実に資格を取得するためのポイント

ここでは、確実に合格するためのポイントを解説します。
現実的な計画立案
現実的な計画を立てるには、以下の手順で進めることが効果的です。
| 学習期間の設定 | 試験日から逆算して必要な期間を算出する 仕事や家庭の予定を考慮した余裕のある期間設定をする 週末や祝日の活用方法を具体化する |
| 学習内容の分類 | 教科・分野ごとの重要度を評価する得意分野と苦手分野の学習時間の配分をする 過去問の解答時間を計測して進度を確認する |
| 1日の学習計画 | 平日:2時間程度の学習時間を確保する 休日:4時間を目安に集中的に学習する 通勤・通学時間の有効活用をする |
| 進捗管理の方法 | 週1回の理解度をチェックする 月1回の模擬試験を受験する 学習記録の継続的な更新をする |
このように、段階的に計画を立てることで、着実に目標達成に近づくことができます。特に、日々の生活リズムに合わせた無理のない計画が長期的な学習の継続につながります。
柔軟な進捗管理
学習計画を状況に応じて調整しながら進めることで、柔軟に進捗管理を行えます。
固定的なスケジュールで学習を進めてしまうと、どうしても集中できないという日でも予定通りに進めようとしてしまいます。その結果、学習効率が下がってしまい、悪循環となる傾向になります。

柔軟な進捗管理の具体例をまとめてみました。
- 予定より早く終わった単元の時間を苦手分野に充てる
- 体調不良の日は軽めの復習に切り替える
- その日の調子や理解度に合わせて学習内容を調整する
柔軟な進捗管理のメリットは、下記の通りです。
- 日々の状態に合わせた最適な学習ができる
- モチベーションを維持しやすくなる
- 結果的に効率良く合格に近づける
長期的な学習計画において特に効果的な進捗管理の方法で、無理なく継続的に学習を進めることができます。
継続できる仕組みづくり
継続できる仕組みづくりとは、長期間にわたって学習を続けられる環境や習慣を意図的に構築することです。
例えば、毎日同じ時間に勉強する習慣をつけたり、小さな目標達成ごとに自分へのご褒美を用意したりする方法があります。
受験勉強は「今日はやる気が出ないから休もう」と思うことも多いものです。

そんなときこそ、続けるための仕組みが重要になります。
自分に合った仕組みがあれば、モチベーションの波に左右されず一定のペースで学習を進められ、確実に実力を積み上げていくことができます。
モチベーションを上げる方法については、こちらの記事で紹介しています。
まとめ

失敗しない資格勉強の計画を立てるためのノウハウについて解説してきました。
まず、自分の現状を把握して、どの程度の学習時間が確保できるかを確認します。そして、試験日から逆算して学習範囲を分割し、毎日少しずつ進めると、気がつけば教科書一周が完了していることに驚くはずです。
特に「今日は第3章を終わらせよう」といった具体的な目標設定が効果的。実際に学習管理表にチェックを入れていくと、達成感を味わいながら次の学習へのモチベーションが湧いてきます。
計画通りに進むことで不安が減り、試験直前にあわてて詰め込む必要もなく、自信を持って本番に臨むことができるでしょう。
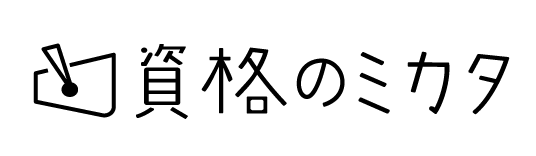





コメント